嵯峨美術大学・油画研究室オフィシャルサイト|TOP|
絵画道場ディスカッションvol.66「広瀬未波の作品をめぐって」
絵画道場ディスカッションvol.66
「 広瀬未波の作品をめぐって 」
2015年11月19日(木)

今回の絵画道場ディスカッションは、短期大学部洋画領域2回生 広瀬未波の展覧会「 オオカミ 」をめぐって開催された。
彼女が発表した作品は素材・技法ともに非常にシンプルな方法で作られている。和紙に墨のみを使用して狼を描いた作品が等間隔で11点展示されており、どの画面の中にも横から見た狼の姿が丁度収まっている。
彼女は幼い頃の落書きから頻繁に狼を描写してきたのだという。今回の絵画道場でも、同じ大きさの和紙に同じ大きさで、何枚も狼の姿を描いている。描き慣れたモチーフに繰り返し向かい合い、その姿や毛並みの流れの変化に「内面」を表現できるのではないかと考えて取り組んだのだそうだ。展示会場では制作した時系列の順に作品が配置され、狼が作者の変化を反映するかのように徐々に表情を変えていた。
作品の細部に注目すると、波打つように引かれた筆のラインで毛並みが表現されている。最初に完成した作品では毛並みの線の一つ一つを丁寧に描こうという意識が画面から観て感じ取れるが、枚数を進めて行くにつれて段々と筆の運びがダイナミックで感情的な激しさを帯びてくる。

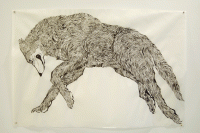

制作のプロセスを作家に質問してみる。
彼女は制作期間中に考えを変化させながら、作品に対しての二通りの向き合い方を経たのだそうだ。作業的に制作をしてから、出来上がった作品から何かを感じ取るべきか、それとも自身の内面に向き合い、思考を練ってから制作に取り掛かるべきか。作品からも見て取れる通り、制作の初期段階では作家自身の感情的な表現をそぎ落として作業的に筆を進めたが、途中から段々と作品に自身の内面を込めようと意識し始めたのだそうだ。
ディスカッションを進める中で、モチーフとして繰り返し描いている狼についても話題が移った。彼女は狼をよく観察して描写している訳ではなく、幼少期からテレビの動物特集などを観ながら自身の中に蓄積されたイメージに沿って筆を進めているのだそうだ。彼女のイメージする狼は野生的で猛々しいもので、動物園で実物の狼を観察した際には飼い慣らされた姿に違和感を憶えたのだと言う。
オオカミの毛並みに自身の内面性を投影した今回の制作ではあるが、オオカミが醸し出していた感情的な雰囲気が、果たして「作家の内面」であったのか、それとも描写を続けるうちに作家の抱く「オオカミのイメージ」に寄っていったのかは作品を観ただけでは判断しにくい部分も感じられた。
シリーズ展開として同じモチーフを繰り返し描く制作行為は多くの作家によく見られるが、作家が特定のモチーフを扱う理由は、当然ながらそれぞれである。例えば、三木富雄が耳の作品ばかりを作り続けたように、モチーフにしている物自体への何らかの執着からストイックな作業で繰り返しそれを作る作家もいれば、下田ひかりの子どものシリーズのように、モチーフは特定でも作品の技法や表現方法によって作品毎の「核」を描き分ける作家もいる。
作品を作る時間の中でも、作家は技術的に描写の要領が良くなっていったり、あるいは思考の揺れや、何かを感じ取り、少しづつ変化してゆく。移り変わってゆく作者の感覚と作品の変化はリンクしているのだろうか。彼女が今回の展示の中で見せた変化が実際にはどういったものであるかは結局のところ本人にしか分かり得ないのだが、自身の内面の奥底にある何かと作品の関係について模索しているようだった。そして、「内面の奥底にある何か」が果たして何であるのかも今回は探り切れなかったが、少なくとも彼女にとって確信的にそれが存在しているのだとすれば、鑑賞者に説明して伝えられる距離感まではその正体を手繰り寄せる必要があるだろう。或いは、作家自身の内面にある「何か」がまだ 説明し難いものだとすれば、やはり純粋な作業を突き詰めた上で、生まれた作品から感じられるものを改めて収穫するべきであるように思えた。
制作初期の心地よい緊張感のある描写にしろ後期のダイナミックで感情的な描写にしろ、彼女は今回の展示に向けての制作の中で作品の向こう側に鑑賞者の視線を察知し、それを目掛けてはまた作品へと「何か」を投じている。その「何か」が無事に届けられるまでの通過点としての今回のディスカッションを終えて、彼女は鑑賞者へ向けて作品を制作するということについて、更に考えを深めたように見えた。
( 文:短期大学部美術分野 教務助手 海野由佳 )
15/12/10
「 広瀬未波の作品をめぐって 」
2015年11月19日(木)

今回の絵画道場ディスカッションは、短期大学部洋画領域2回生 広瀬未波の展覧会「 オオカミ 」をめぐって開催された。
彼女が発表した作品は素材・技法ともに非常にシンプルな方法で作られている。和紙に墨のみを使用して狼を描いた作品が等間隔で11点展示されており、どの画面の中にも横から見た狼の姿が丁度収まっている。
彼女は幼い頃の落書きから頻繁に狼を描写してきたのだという。今回の絵画道場でも、同じ大きさの和紙に同じ大きさで、何枚も狼の姿を描いている。描き慣れたモチーフに繰り返し向かい合い、その姿や毛並みの流れの変化に「内面」を表現できるのではないかと考えて取り組んだのだそうだ。展示会場では制作した時系列の順に作品が配置され、狼が作者の変化を反映するかのように徐々に表情を変えていた。
作品の細部に注目すると、波打つように引かれた筆のラインで毛並みが表現されている。最初に完成した作品では毛並みの線の一つ一つを丁寧に描こうという意識が画面から観て感じ取れるが、枚数を進めて行くにつれて段々と筆の運びがダイナミックで感情的な激しさを帯びてくる。

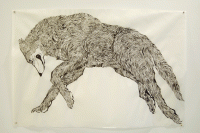

制作のプロセスを作家に質問してみる。
彼女は制作期間中に考えを変化させながら、作品に対しての二通りの向き合い方を経たのだそうだ。作業的に制作をしてから、出来上がった作品から何かを感じ取るべきか、それとも自身の内面に向き合い、思考を練ってから制作に取り掛かるべきか。作品からも見て取れる通り、制作の初期段階では作家自身の感情的な表現をそぎ落として作業的に筆を進めたが、途中から段々と作品に自身の内面を込めようと意識し始めたのだそうだ。
ディスカッションを進める中で、モチーフとして繰り返し描いている狼についても話題が移った。彼女は狼をよく観察して描写している訳ではなく、幼少期からテレビの動物特集などを観ながら自身の中に蓄積されたイメージに沿って筆を進めているのだそうだ。彼女のイメージする狼は野生的で猛々しいもので、動物園で実物の狼を観察した際には飼い慣らされた姿に違和感を憶えたのだと言う。
オオカミの毛並みに自身の内面性を投影した今回の制作ではあるが、オオカミが醸し出していた感情的な雰囲気が、果たして「作家の内面」であったのか、それとも描写を続けるうちに作家の抱く「オオカミのイメージ」に寄っていったのかは作品を観ただけでは判断しにくい部分も感じられた。
シリーズ展開として同じモチーフを繰り返し描く制作行為は多くの作家によく見られるが、作家が特定のモチーフを扱う理由は、当然ながらそれぞれである。例えば、三木富雄が耳の作品ばかりを作り続けたように、モチーフにしている物自体への何らかの執着からストイックな作業で繰り返しそれを作る作家もいれば、下田ひかりの子どものシリーズのように、モチーフは特定でも作品の技法や表現方法によって作品毎の「核」を描き分ける作家もいる。
作品を作る時間の中でも、作家は技術的に描写の要領が良くなっていったり、あるいは思考の揺れや、何かを感じ取り、少しづつ変化してゆく。移り変わってゆく作者の感覚と作品の変化はリンクしているのだろうか。彼女が今回の展示の中で見せた変化が実際にはどういったものであるかは結局のところ本人にしか分かり得ないのだが、自身の内面の奥底にある何かと作品の関係について模索しているようだった。そして、「内面の奥底にある何か」が果たして何であるのかも今回は探り切れなかったが、少なくとも彼女にとって確信的にそれが存在しているのだとすれば、鑑賞者に説明して伝えられる距離感まではその正体を手繰り寄せる必要があるだろう。或いは、作家自身の内面にある「何か」がまだ 説明し難いものだとすれば、やはり純粋な作業を突き詰めた上で、生まれた作品から感じられるものを改めて収穫するべきであるように思えた。
制作初期の心地よい緊張感のある描写にしろ後期のダイナミックで感情的な描写にしろ、彼女は今回の展示に向けての制作の中で作品の向こう側に鑑賞者の視線を察知し、それを目掛けてはまた作品へと「何か」を投じている。その「何か」が無事に届けられるまでの通過点としての今回のディスカッションを終えて、彼女は鑑賞者へ向けて作品を制作するということについて、更に考えを深めたように見えた。
( 文:短期大学部美術分野 教務助手 海野由佳 )
15/12/10

旧・京都嵯峨芸術大学 油画分野(オフィシャルサイト)
